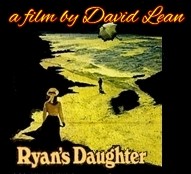映画『ライアンの娘』はメロドラマにはなりえない。登場人物のいずれもが自分に忠実であるだけだ。それがドラマとなるのは、当時の歴史背景という不動の骨組みに支えられてのこと。だから、素朴なストーリーでありながら、重厚な印象を焼き付けられるのだろう。
時代はちょうど百年前の1916年。第一次大戦のさなかで、アイルランドの宗主国イギリスはドイツを相手に戦っている。すでにこの年、アイルランド義勇軍がドイツの支援のもと、独立に向けて蜂起し、英軍に鎮圧されて終わった。アイルランドの南、海辺の小さな村でも、反英闘争に参加する若者たちが、荒天のなか、ドイツから密輸した武器を陸揚げしようとしている。
映画についてはここまでにして、アイルランドがどれほどドイツとの結びつきを重視していたかを課題にしてみる。
敵の敵は味方、という公式をもってすると、アイルランドが、敵たるイギリスの敵、ドイツと結びつくのはわかりやすい。おまけに隣人として付き合う必要がなければ、相手の「あばた」が気に障ることはない。
加えて、アイルランド語(ゲール語)には気息音があり、ドイツ語のバッハやイッヒなどでわかるとおり、その音はきわだって聞こえる。しかもひんぱんに出てくるので耳障りといえなくもないが、アイルランド人がドイツ語に親しみを感じても不思議ではない。
そういうあれこれが重なって、アイルランド人はドイツ贔屓と思えふしがある。(これはドイツとドイツ人を知らない場合にかぎってのことだ。現実には、寝坊のアイルランド人と早起きのドイツ人がうまくやっていけるとは思えない)。
というところで、「黄毛のアン」のことを語るきっかけができた。
1973年、わたしはアイスランドでの学業を無事に終え(学位を取得して)、その夏いっぱいヨーロッパで過ごすことにしていた。まず最初はコペンハーゲン大学の外国人向けデンマーク語コース。クラスにはフランス人の翻訳家がいたりして、学ぶというより、各自の体験をデンマーク語を介して楽しむ活気ある場だった。それも最後の数日を残したまま、わたしはデンマークを離れねばならなかった。すでに申し込んであったハイデルベルク大学の夏期ドイツ語コースが始まるのだ。
ハイデルベルクには朝到着する列車でたどりつき、大学事務局へ行って、わたしはようやく自分に割り当てられた滞在先を教えられた。
それは二人の育ち盛りの子供のいるドイツ人の家で、妻は看護師、夫は医療検査技師として働いている。じきわかったことだが、一家は毎年夏、外国人女子学生を二人寄宿させ、その間、ヨーロッパの南をめざしてキャンピングカーを引いていって、そこに長逗留してバカンスを送るのだ。留守中の家をみてもらい、その間の家賃もいただくという、じつに合理的なやり方だ。その夏の彼らの行き先はサルデーニャだった。
翌日、もうひとりの寄宿人が到着した。アイルランドのゴールウェイ出身のアン・L。年齢はわたしと同じくらい、小柄なこともわたし並だったが、農家の生活で身についた落ち着きとたくましさとが感じられた。ゴールウェイ大学の夜間コースでドイツ語を学びはじめたところだという。
ホスト・ファミリーは数日かけて、家の内外のこと、町なかの店やそのほか知っておくべき場所のこと、さらには、訪れるべきビヤホールの名前をわたしたち二人に伝授してくれた。やり手で熱意にあふれる妻は、頭の上にいつでも気遣いの雲をむくむく湧かせているかのようで、ともかく何でも話してくれた。
「上の娘は利発だし、ここのアメリカン・スクールに行かせているのだけど、下の息子ったら、小学四年になるのにまだ子供っぽさが抜けてなくて、この秋、進路を決める大事な試験を受けなきゃいけないのに、これじゃ、職業コースに行かされてしまうんじゃないかと心配で」
毎夏、留守番をつとめる女子学生二人の国籍選びも、彼女の判断によっていた。
「今年は日本人とアイスランド人ってリクエストしておいたんだけど、アイスランド人の女子はいなかったので、学生課のほうで気をきかせて、アイスランドに留学してた日本人とアイルランド人を選んでくれたってわけ」
のちにある友人にこの話をしたら、
「そりゃ幸運だった。アイスランド人に留守番をさせたら、どんなことになるか知らないんだな、その人たち。ドイツじゅうのアイスランド人を呼び寄せて、夜な夜な宴会オージーをやらかしてたよ」
さて、愛すべきアンのことだ。ブロンドになりそこねた芥子色といったらいいのか、黄色系の明るい色の髪は短めで、地味にかわいい印象を与える女の子だった。彼女がドイツのサマーコースにやってきたのは、婚活の領域を広げるためであることはじきに知れた。それだって、話のはしばしから察せられる程度のほほえましいものだった。
ホスト・ファミリーの妻が、「彼女、ずっと田舎暮らしで、人ずれしてなくていい娘こなんだけど、ちょっと心配なのよ」と評したのは、わたしには余計な心配のように思えたが、これまで数多くの若い外国娘と接してきて、なかには羽目をはずして困った事態におちいるのもいたのだ。
それから一家はキャンピングカーとともに出発した。帰宅は、サマーコースが終わる数日前になるとのことだった。
留守宅を自由に使える女子たちからすると、「ヒャッホー!!」という気分だった。
それでなくてもハイデルベルクは人気の観光地だ。町なかは、観光客に加えて、町の大学、語学学校の夏季講習で滞在する外国人学生であふれていた。若い外国人だらけの場所は、征服感にも似た高揚した空気を漂わせていた。そもそもわたしはなぜドイツ語学習のためにハイデルベルクを選んだのか、今ではさっぱり思い出せない。
当然のようにわたしは初級クラスの授業を受けたのだが、アイスランド語とデンマーク語を身につけたあと、ドイツ語は自然に体に流れ込んだ。動詞の不規則変化は自分ですでに知っているとしか思えなかった。
そういうわけで、授業に出たあとは、何のわずらいもなく、町のあちこちを訪ねて回った。エクスカーションも用意されていた。アンといっしょに行くことが多かった。夜、町のビヤホールに出かけることで、いつもアンとわたしの意見は一致した。
(次回に続く)
(次回に続く)