前々回(1971年の北アイルランド)から続く。
いくらなんでも出来すぎだった、あの場面は。映画の撮影現場だと言われれば納得してしまいそうだった。英国軍が駐留する町デリーの、見るからに貧しいカトリック系住民地区に、これみよがしに監視ポストが設置され、英国兵の歩哨が立っている。そこへ地元の若い女が駆け寄ってきて、ふたりはひしと抱き合う。その姿を、住民は険しい表情で見ている。
ずっとあとになって思い起こしたとき、そこには単なる宗教の対立にとどまらない愛憎のこじれようが見てとれた。アイルランド問題が解決にいたらないのは、カトリック、プロテスタントのそれぞれが、宗教的信条で外部に対する守りを固めておきながら、その内部では愛憎感情を無防備なまでにはぐくんでやまないからではなかろうか。
この時のことを鮮明な図柄としてありありと思い出し、それが記憶にしっかり焼きついて離れなくなったのは、のちに観た映画のおかげもある。
東京に住み始めてわたしは映画フリークとなった。いわゆる名画座が全盛の時代で、2本立て、3本立てで近作、旧作がみられる。しかも低料金だった。だから、予備知識もないまま、目の前の映画の流れにともかく身をゆだねることもよくあった。すると、それが思いがけない佳作だったり、そうでなくても何らかの「発見」があったりして、知的快感を呼び起こした。車窓の外の景色を飽かず眺めて楽しんでいられるのと同じだ(少なくともわたしに関しては)。
ともかく、向こうからやってきたというしかない。そんな遭遇のしかたであの映画に出くわしたのだ。
とある名画座に行ったのは、観たい作品があってのことだった。館内の暗がりに足を踏み入れたとき、併映作品がまだ終わってなくて、最終シーンを映し出していた。今よりかなり古い時代、数人の男女が荷物を抱えて街道を歩いていく。その一行を、道沿いの家々の住人が外に立って、あるいは戸口や窓から顔をのぞかせて、憎悪もあらわに見送っている。
「ああっ、アイルランドだ!」
わたしは声にならない声を上げた。デリーで目撃することになったあの場面が、そのシーンとかっちり合わさった。
まさしくそれはデヴィッド・リーン監督の『ライアンの娘』、独立前のアイルランドを舞台とする映画だった。
アイルランド南部の寒村を舞台に、自分の境遇を物足りなく思っている人妻ロージーは、赴任してきた英国軍将校と恋に落ちる。その頃のアイルランドは、イギリスから独立する企てが鎮圧されて終わり、まもなくアイルランド独立戦争が起きようとしている緊迫した時期である。ロージーはアイルランドに対する裏切り者とみなされ、村人たちから制裁を加えられ、最後に、妻を気づかう夫とともに村から出て行く。あの憎悪にみちた視線に見送られながら。
この監督による『アラビアのロレンス』や『ドクトル・ジバゴ』といった作品は、見逃すわけにいかない歴史的大作だった。だのに、1970年に公開された『ライアンの娘』がわたしの関心を引かなかったのは、あるいはメロドラマ臭ふんぷんの宣伝イメージに拒否反応が働いたせいだったか。
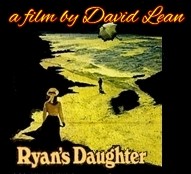

0 件のコメント:
コメントを投稿